デューン 砂の惑星
| 年 | 1984年 |
|---|---|
| 時間 | 137分 |
| 監督 | デヴィッド・リンチ |
惑星アラキスは宇宙で最も価値ある香料メランジの産地。だがそこは砂漠に覆われ雨の降らない過酷な惑星でもあった。銀河を統べる大王皇帝シャッダム4世の命令でアラキスに赴任したレト・アトレイデ公爵と息子のポウルは、アラキス前任者でアトレイデ家の宿敵ハルコンネン男爵との戦いに巻き込まれていく。砂漠の民フレーメンを味方につけたポウルはメランジの力で秘めたる力に目覚めハルコンネンとの対決に臨むのだった──。
小説「デューン 砂の惑星」の映画化作品です。小説が好きだったので映画も期待して見に行った記憶があります。話の筋を知っているので、内容は難しくなかった(むしろ分かりやすかった)のですが…。小説4冊分を2時間ちょっとに収めているので、話の展開が速い、速い、微妙な心理やドラマを掘り下げる時間などなく、状況変化も台詞で説明しながら飛ばす、飛ばす、もうほとんどダイジェスト。もし映画を見てデューンをもっと詳しく知りたくなったら小説をお読み下さい──て感じでした(^^;。
小説の映画化の場合、小説ファンから見たら「あのシーンをどう映像化したのかな」も楽しみの1つです。映像化が良ければ話の少々の端折りや展開に雑なところがあっても許せるものですが、今作はちょっと…かなり…微妙だったような。個人用のシールドの描写では吹きそうになった…いや斬新です、文章だけではイメージしにくかったシールドってこういうものだったのか!と思うことは出来たです、しかしもうちょっと何とかならんかったんか…。
中でも個人的にがっかりだったのが砂虫(サンドウォーム)。制作陣は頑張ったんだと思うのですが、巨大なミミズみたいで、もうちょっとこう…これじゃない感が。アラキスの生態系やメランジ生成に関わる作品の肝みたいな生物なんだからさ、動きにぞぞぞっとさせてくれるとか、デューンのイメージ代表になるような荘厳さを出すとか、ナウシカの王蟲のように人間キャラを喰ってしまうほどの存在感と魅力が欲しかったです。
全体に特撮が今一つなところが多かったですが、ゴテゴテした中世+スチームパンクみたいな装飾と衣装は悪くなかった。独自の異様な存在感がありました。ハルコンネンはイメージぴったりにはまってたし、フェイドもよかった。メンタートたちの眉毛には笑いましたが。
<ネタバレ>
映画だけでは意味不明なところもあるかも知れないので、簡単な補足をしておきます。一応、恒星間航行が出来るようになった人類の未来が舞台です。映画では説明省略されてますが、かつてあったAIをやめて人間の能力を開発する方向へ進んだということになってます。メンタートは人間コンピューターで、この世界で必要な計算処理は彼らが担っています。ベネ・ゲセリットはクイサッツ・ハデラッハを生み出すための繁殖計画を行っており、そのために女性の精神を訓練して魔女と呼ばれるほどの能力開発を行ってます。メランジは麻薬の一種で毒です。毒は使い方次第で薬にもなるので、老人病の特効薬として使われてます。メランジを大量に常用するとメランジ中毒になり眼が白目も含めて青色に染まります。「生命の水」は砂虫が出す液体で強力な毒。これを体内で分解できる者が教母になります。クイサッツ・ハデラッハはその男性版。
レト公爵は皇帝の従兄弟だが人望がある。それを疎ましく思う皇帝はアラキスからハルコンネンを去らせ、アトレイデをアラキスに赴任させることで、ハルコンネンがアトレイデを襲うよう仕向ける。メランジの利権は莫大な富を生むので、ハルコンネンが黙って宿敵のアトレイデに譲るはずはないからだ。その結果、ポウルは母と砂漠に追われることになり、フレーメンの指導者になって打倒ハルコンネン!となるのですが、クイサッツ・ハデラッハをかなり拡大解釈してるなあ。
私はエンターテイメント好きなので、エンターテイメントな方向に振られるのはかまわないのですが、クイサッツ・ハデラッハとなったポウルに雨を降らせちゃったのはどうなのか。おかげでラストで原作とは違う話になっちゃいました。メランジは意識を広げるものであり、メランジで覚醒した男性は女性の見ることの出来ない領域まで見られるようになり、多くの未来を知ることが出来るようになる。それがクイサッツ・ハデラッハ(予言者)なんですが、映画では砂虫を心で支配したり雨を降らせたり声だけで物を破壊したり出来る「超人」な方向へ行ってしまいましたね。まあその方がエンターテイメント的には映えるけどね。ポウルの妹のエイリアも超能力者になってるし。なお、ポウルたちが使ってた音を使う武器は映画オリジナルです。
ところで物語に関与しないイルーラン姫が何故語り役だったのかは、小説では章の冒頭に必ずイルーラン姫がまとめた文書からの引用が載っているので、それに習ったものと思われます。

 2022/02/14
2022/02/14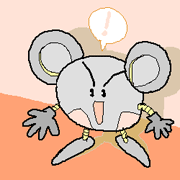
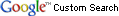
 ゴジラ-1.0
ゴジラ-1.0 ターミネーターシリーズ 時系列のまとめとタイムパラドックス考察
ターミネーターシリーズ 時系列のまとめとタイムパラドックス考察 ウエストワールド シーズン1・2 まとめと考察
ウエストワールド シーズン1・2 まとめと考察 エイリアン:ロムルス
エイリアン:ロムルス ゴジラxコング 新たなる帝国
ゴジラxコング 新たなる帝国 アンチャーテッド
アンチャーテッド メールはこちらへ
メールはこちらへ