アイ・アム・レジェンド
| 年 | 2007年 |
|---|---|
| 時間 | 100分 |
| 監督 | フランシス・ローレンス |
はしかウイルスから作られたガンの特効薬が変異し、それから3年──。人類はほぼ死滅し、変異ウイルスへの免疫を獲得した僅かな者もほとんどが人間を捕食する凶暴なダーク・シーカーと化していた。元陸軍中佐で科学者のネビルはNYでただ1人の人間の生き残りとなり、生存者を探すメッセージを発信しながら愛犬のサムと廃墟となった町で暮らしていた。だがダーク・シーカーへの血清の研究に光が見えた時、彼らのリーダーに奇襲をかけられる──。
何かで見てはいるのですが、映画館で見た記憶がないので地上波だったのかな。スカパーのザ・シネマでやっていたのでこの機会に見直してみました。ガン特効薬が死のウイルスに変異して、しかも空気感染するからあっという間に世界中に広がって人類はほぼ死滅、死を免れた感染者も人間を喰らうだけの凶暴なゾンビのようなものになるという設定。作中ではダーク・シーカーと呼ばれてました。光に弱いので日中は出てこない。夜や暗闇の中で徘徊。だから陽が出ている間は外で活動できる。夜になると厳重に戸締まりして彼らを防ぐ。そのパターンでネビルは3年生き延びたということですね。
感染者の中にはダーク・シーカーになるのを免れた人間も僅かながら存在します。ネビルもダーク・シーカーにならずにすんだ免疫保持者。しかしダーク・シーカーにはならなくても食べられては終わりなので、連中を避けねばならないことに変わりはない。ネビルは科学者なのでダーク・シーカーになった人々を治す血清の開発も1人で黙々と進めてます。
前半はネビルの回想を交えながら廃墟のNYで1人暮らす様子を描きつつ、夜や暗闇への緊張感も盛り込んで、淡々としながらドキドキする描写。昼間は大丈夫なら夜や暗闇を避ければ問題なく暮らしていけそうですが、血清開発のためにはそうもいかない。ネビルは科学者としてNYから死のウイルスを出してしまったことに責任も感じてるようです。
<ネタバレ>
マウスで実験を繰り返し、希望がありそうなら感染者で実験する。そのためには感染者を研究室に連れてこなければいけないので、危険を冒して感染者狩りをする。壁に貼られた実験者のリストを見ると相当数の人体実験を繰り返してきたことが分かる。マウスの1匹に血清が効いたので、今度こそ──の思いを込めて新たに狩ったのは若い女性。だがこれに感染者のリーダー格が強く反応した。もしかしたら恋人だったのかもしれない。
ダーク・シーカーは言葉での意思疎通は出来ないようだけど、多少の知性はありそうです。マネキンを動かしてネビルの気をひいたり、罠を仕掛けてみたり。彼らの攻撃でネビルは愛犬のサムを失う。サムには亡くした娘の思いも入っており、サムがいたことで何とか保っていた正気が失われて夜にダーク・シーカーの群れに突っ込むという自暴自棄に陥る。
だがネビルの住居を突き止め執念で追ってくるダーク・シーカーの男に、彼にも奪われた女性への思いがあることを感じて、彼らから逃れるのは不可能だと悟る。無線を聞いてやってきた女性と少年に血清投与が効いた感染女性の血液を託したネビルは、ダーク・シーカーたちもろとも自爆して2人を逃す。
Wikipediaを見たら、原作小説ではラストで価値観の逆転が行われることがキーになっていたようです。でも今作だとそこまでは行ってなくて、レジェンドの意味も小説とは違う。小説では感染者を襲う伝説の怪物という意味で「レジェンド」が使われていて、つまり本当の悪者は人間を襲う感染者ではなくて、感染者を襲う人間の方だった──ということになっているのですが、映画では血清を開発した人として伝説(レジェンド)になったという使われ方をしていて、英雄扱い。うーん、SFとしては小説の展開の方が秀逸でメッセージ性もあるのに、何で映画では変えちゃったのかなあ。
せめてネビルが、人類のためと思って自分がしてきたことが、感染者側から見たら自分の方がダーク・シーカーだったもしれない…と気付いた上での自爆だったらもっと深みが出たのに、そこがちょっと残念。深読みすれば実は気付いてたと解釈することも出来るような描写なんですが、ラストの「血清を開発した人間として伝説になった」の一文で台無しになってますからね…。
*後で検索してみたら、別エンディングというのがあって、それこそが私の感じた疑問を解消してくれるバージョンだったらしい。本来は小説のように価値の逆転を行う予定だったらしいですが、試写会で評判が悪かったため急遽ラストを変更することになったとか。積み重ねてきたエピソードに対してラストが唐突に感じられたのはそのせいだったのですね。別エンディングなら壁の写真も知性の描写も伏線として生きるし納得。ラストを変えなければ秀逸なSFとして評価されたろうに、ただのゾンビパニックになってしまったのが惜しかった作品。

 2018/12/13
2018/12/13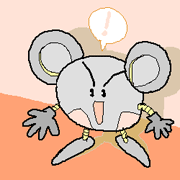
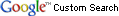
 ゴジラ-1.0
ゴジラ-1.0 ターミネーターシリーズ 時系列のまとめとタイムパラドックス考察
ターミネーターシリーズ 時系列のまとめとタイムパラドックス考察 ウエストワールド シーズン1・2 まとめと考察
ウエストワールド シーズン1・2 まとめと考察 エイリアン:ロムルス
エイリアン:ロムルス ゴジラxコング 新たなる帝国
ゴジラxコング 新たなる帝国 アンチャーテッド
アンチャーテッド メールはこちらへ
メールはこちらへ